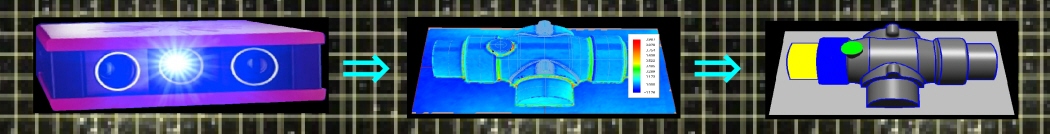「グリーン技術」とは、環境への影響を減らし、持続可能性を高めることを目的とした技術や実践のことを指します。以下は、その種類と応用例です:
- グリーンケミストリー:化学物質のライフサイクル全体において、人体や環境への負荷を低減するコンセプトと技術の総称です。安全で持続可能、かつ環境に優しい方法で化学物質や化学製品を製造することを目指し、地球環境との共生や社会的要請への充足、経済の合理性を基本理念としています。
- グリーン水素:再生可能エネルギーを使って水を電気分解することによりCO2を排出せずに製造される水素の方法です。温室効果ガスを排出しないため、次世代エネルギーとして期待されています。ブルー水素やグレー水素など、環境への影響に基づいて色分けされた他の水素も存在します。
- 気候変動対策のグリーン技術:再生可能エネルギーのコスト低下に寄与する技術や、グリーン水素やCO2の回収・貯留などの新技術の開発が進んでおり、脱炭素化に向けた重要な技術です。
- グリーンIT:情報技術(IT)を活用して環境負荷を低減する取り組みです。ITの省エネ化(情報システムそのものの環境負荷低減)とITによる省エネ化(情報システムによる環境負荷低減)の2つの側面があります。例えば、低消費電力のサーバーやPC、消費電力を抑えた半導体製品の活用などがあります。
これらはグリーン技術の例の一部であり、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源、エネルギー効率技術、持続可能な水管理、環境に優しい建築材料など、さまざまな他の実践も含まれます。グリーン技術の共通の目標は、より持続可能で環境に優しい未来を創造することです。
 |
| <トップページへ> |